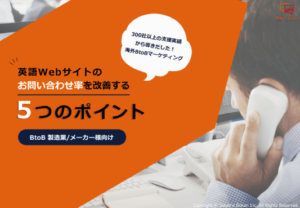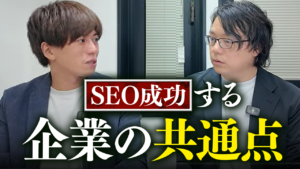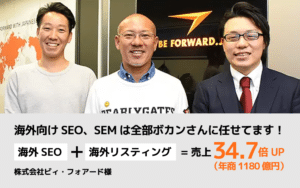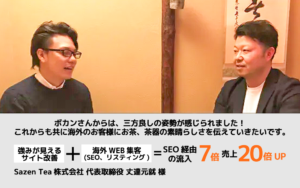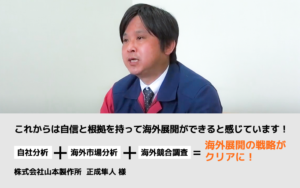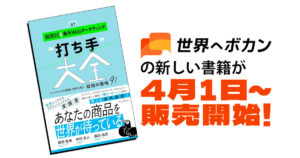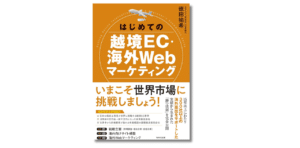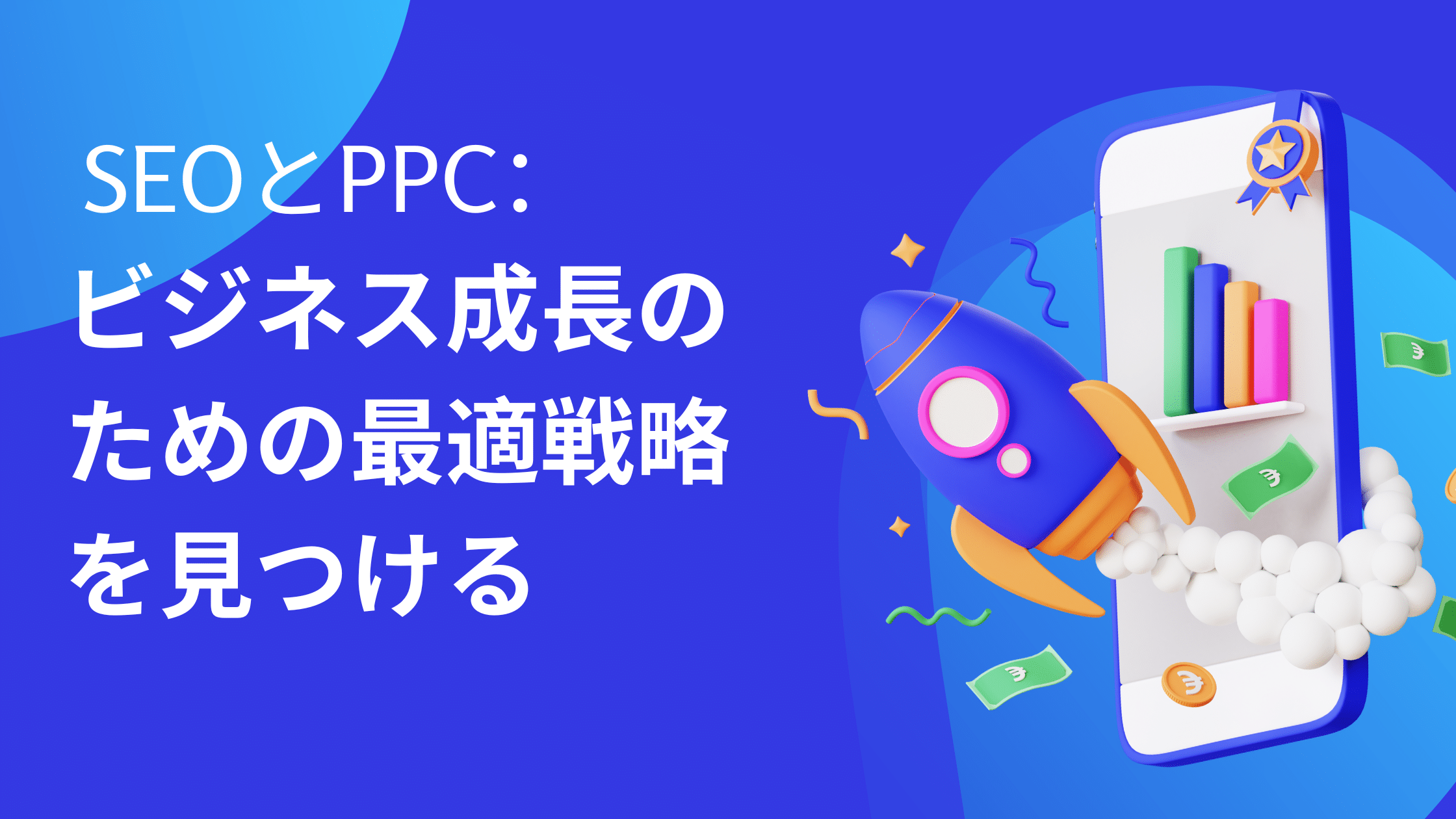海外マーケティングブログ
OEMとは?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説
- 2025.05.21
- 海外BtoB
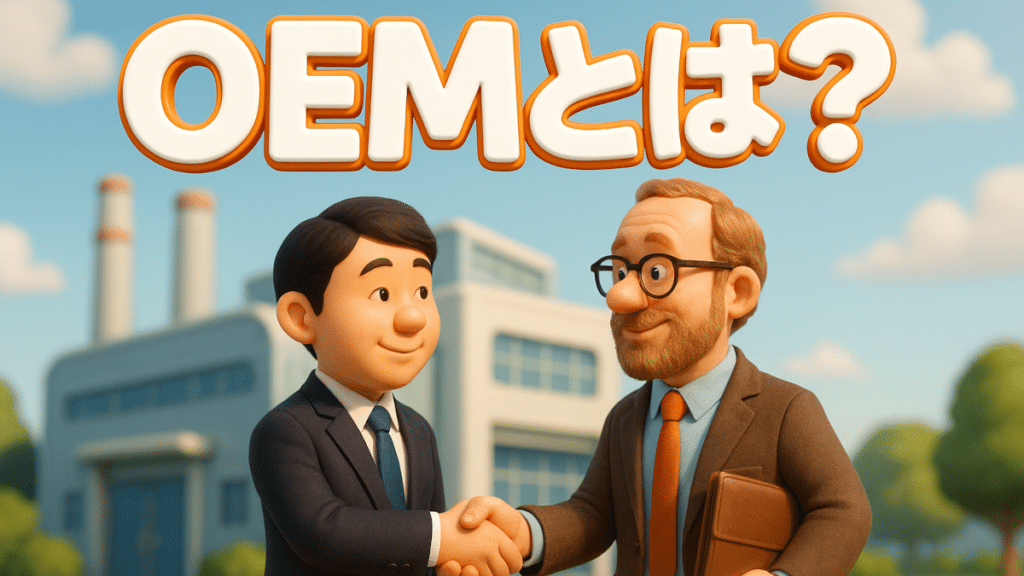
OEMとは?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説
「OEM」という言葉を聞いたことがありますか?
ビジネスの世界では頻繁に使われますが、実は私たちの生活に欠かせない、とても身近なものです。
例えば、コンビニで手に取るプライベートブランドのお菓子、毎日使うスマートフォンの部品、好きなアパレルブランドの洋服などなど。
これらの中には、そのブランドの会社ではなく、別の専門メーカーが製造しているものが数多くあります。
このように、他社のブランド名で販売される製品を、代わりに製造するビジネスモデルを「OEM」と呼びます。
この記事では、OEMの世界をゼロから徹底的に解説します!
「これから自分のブランドで商品を作ってみたい」
「ビジネスの仕組みを深く理解したい」
OEMの定義と歴史、ODMとの明確な違い、契約の流れや費用構造、そして成功の鍵を握るパートナー選びのポイントを解説します。
OEMの大枠が理解でき、ビジネスの新たな可能性が見える内容になっています!
OEMの定義と歴史
OEMとは「Original Equipment Manufacturer」の略語で、日本語では「相手先ブランドによる生産」と訳されます。
簡単に言えば、製品の企画や設計は自社(委託者)で行い、その仕様に基づいて製造だけを外部のメーカー(受託者)に委託するビジネスモデルです。
完成した製品は、委託者の自社ブランド(プライベートブランド)として市場で販売されます。
この仕組みの起源は、1950年代のアメリカ家電業界に遡ります。
大手ブランドが自社で工場を持たずに新製品をスピーディーに市場投入するため、外部の製造能力を活用したのが始まりと言われています。
日本では1980年代、パソコンの普及と共に、部品の効率的な調達方法としてOEMが浸透しました。
歴史を振り返ると、OEMが世界的に拡大した背景には2つの大きな流れがあります。
一つは、サプライチェーンの最適化です。
製品開発、製造、販売といった工程を分業し、それぞれの専門家が担うことで、全体の効率と品質を高める動きが加速しました。
もう一つは、グローバル競争の激化です。
国際標準の整備により、遠隔地の工場でも品質を担保した取引が容易になり、世界中から最適な製造パートナーを探せるようになりました。
現在、OEMは食品、化粧品、アパレル、家電、自動車部品など、考えられるほぼ全ての工業製品分野で活用されています。
経済産業省の調査によると、国内のOEM関連取引は年々増加傾向にあり、企業の生産戦略において不可欠な選択肢となっています。
より詳しい統計データは経済産業省の統計ページなどで確認できます。
OEMとODMの明確な違い
OEMを理解する上で、必ず比較対象となるのが「ODM(Original Design Manufacturing)」です。
両者は似て非なるもので、この違いを理解することが、自社に最適な生産戦略を選ぶための第一歩となります。
最大の違いは、「製品の設計・開発をどちらが主導するか」という点です。
- OEM:委託者(ブランド側)が製品の企画・設計を行い、製造のみをメーカーに委託する。
- ODM:受託者(メーカー側)が製品の企画・設計・開発から製造まで一貫して行い、委託者(ブランド側)はその完成品に自社ロゴを付けて販売する。
以下の比較表で、両者の特徴を整理してみましょう。
| 項目 | OEM (製造委託) | ODM (設計・製造委託) |
|---|---|---|
| 担当範囲 | 製造のみ | 企画・開発・設計から製造まで |
| 主導権 | 委託者(ブランド側) | 受託者(メーカー側) |
| 委託者のメリット | ・ブランドの独自性やコンセプトを忠実に反映できる ・自社の技術や設計思想を活かせる |
・製品開発の知識やノウハウが無くても製品化できる ・開発期間を大幅に短縮し、コストを削減できる |
| 委託者のデメリット | ・自社で製品開発を行うための時間とコストがかかる ・開発力がないと利用できない |
・メーカー主導の開発になるため、独自性を出しにくい ・他社ブランドと類似した製品になる可能性がある |
例えばスマートフォン業界では、グローバルブランドX社が筐体デザインやコア技術を自社で主導し、その組み立てを台湾の巨大EMS企業に委託するのが典型的なOEMです。
一方で、小型家電を販売したいY社が、中国メーカーがすでに開発済みの加湿器のデザインを気に入り、日本市場向けの安全基準に適合させる微調整だけを依頼して自社ブランドで販売するのがODMに近い手法です。
自社の状況に合わせて、「ブランドの独自性を追求したいならOEM」、「スピーディーに市場参入したいならODM」といった戦略的な使い分けが重要になります。
【委託者側】OEMの5つのメリット
多くの企業がOEMを活用するのには、明確な経営上のメリットがあるからです。
ここでは委託者(ブランド側)の視点から、5つの大きな利点を解説します。
1. 設備投資の大幅な抑制
工場建設や生産ラインの導入には、数十億、数百億円といった巨額の初期投資が必要です。
OEMを活用すれば、これらの設備投資を完全に回避できます。
浮いた資金を、製品の研究開発、ブランディング、マーケティングといった、ブランド価値を直接高めるための活動へ戦略的に再配分することが可能になります。
2. 開発から販売までの期間短縮(短納期)
すでに稼働している専門メーカーの生産ラインを活用するため、ゼロから設備を準備する場合に比べて、試作品の製作から量産開始までの期間を劇的に短縮できます。
市場のトレンドや消費者のニーズが目まぐるしく変わる現代において、この対応速度の向上は非常に大きな競争優位性となります。
3. 専門メーカーの高度な技術を活用可能
OEMメーカーは、特定の分野で長年培ってきた専門技術、ノウハウ、そして熟練した人材を抱えています。
自社単独では実現が難しい高度な加工技術や、厳しい品質管理体制を、委託という形で活用できます。
これにより、高品質な製品を安定的に生産し、ブランドの信頼性を高めることにつながります。
4. 需給変動に応じた柔軟な生産と在庫リスクの最小化
自社工場を持つと需要の波に合わせて生産量を調整するのは容易ではありませんが、OEMなら市場の反応を見ながら柔軟に生産量をコントロールできます。
最初は小ロットで生産し、人気が出れば追加発注するという段階的な対応が可能なため、売れ残りによる過剰在庫のリスクを最小限に抑えられます。
5. スケールメリットによるコスト削減
大規模なOEMメーカーは、複数のブランドから大量に受注することで、原材料や部品を安価に一括調達しています。
このスケールメリットを享受できるため、自社で小規模に生産するよりも、結果的に製品一個あたりの製造コストを下げられる場合があります。
【委託者側】OEMの5つのデメリットと対策
メリットの大きいOEMですが、もちろんリスクや注意点も存在します。
これらを事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。
1. 自社に製造ノウハウが蓄積されない
製造を完全に外部依存するため、自社内に生産技術や品質管理の知見が蓄積されません。
将来的に製造を内製化したい場合や、メーカーとの技術的な交渉を行う上で不利になる可能性があります。
【対策】 メーカーを単なる発注先と捉えず、積極的にコミュニケーションを取りましょう。
定期的な工場監査や技術ミーティングを通じて、製造工程への理解を深める努力が重要です。
2. 品質管理の難易度が高い
製造現場が外部にあるため、品質を直接コントロールすることが困難です。
万が一、委託先で品質不良が発生すれば、原因究明に時間がかかり、最終的に自社ブランドの信用が大きく損なわれます。
【対策】 契約前にメーカーの品質管理体制(ISO9001などの認証取得状況、検査基準)を徹底的に確認します。
契約書に詳細な品質基準と、不良品発生時の責任分界点を明記することが不可欠です。
3. 機密情報(設計・技術)の漏えいリスク
製品の設計図や独自の技術情報、販売計画などを外部と共有するため、常に情報漏えいのリスクが伴います。
特に独自性の高い製品の場合、情報流出は致命的な損害につながりかねません。
【対策】 取引開始前に、必ず秘密保持契約(NDA)を締結します。
契約内容には、秘密情報の定義、目的外使用の禁止、契約終了後の情報破棄義務などを具体的に盛り込みましょう。
4. コスト構造が不透明になりやすい
提示される見積もりの内訳(材料費、加工費、管理費など)が詳細に開示されないケースがあり、コストが適正価格なのか判断しにくい場合があります。
いわゆる「ブラックボックス化」です。
【対策】 複数のメーカーから相見積もりを取り、比較検討することが基本です。
また、価格交渉の際には、コストの内訳を可能な範囲で開示してもらうよう求め、透明性の高い取引を目指します。
5. 生産計画の自由度が低い
委託先の生産ラインの稼働状況に、自社の生産計画が左右されます。
特に繁忙期には、急な増産依頼に対応してもらえなかったり、納期調整が難航したりすることがあります。
【対策】 年間の大まかな生産計画を早期に共有し、メーカー側とすり合わせを行います。
また、1社に依存せず、複数の委託先を確保しておく(サプライヤーの多角化)ことも有効なリスクヘッジとなります。
OEM契約の具体的な流れ【7ステップ】
実際にOEMで商品を作る場合、どのような手順で進むのでしょうか。
ここでは企画から販売までを7つのステップに分けて解説します。
- 要件定義・企画
「誰に、何を、どのように届けたいか」という製品コンセプトを固めます。
ターゲット市場、製品仕様書、販売目標、予算、希望ロット数などを明確に定義します。
この最初の設計図が、プロジェクト全体の成否を分けます。
- OEMメーカーの選定・調査
要件に合うメーカーを探します。
インターネット検索のほか、業界専門の展示会への参加や、ビジネスマッチングサイトの活用が有効です。
技術力、実績、品質管理体制(ISO9001認証など)、財務状況を多角的に評価します。
- 問い合わせとNDA(秘密保持契約)締結
候補となるメーカーに問い合わせ、要件を伝えます。
具体的な情報交換に進む前に、必ずNDAを締結し、情報漏えいを防ぐ手立てを講じます。
- 打ち合わせ・試作品製作
メーカーの担当者と詳細な仕様を詰め、試作品(サンプル)の製作を依頼します。
完成したサンプルをデザイン、機能、品質などあらゆる角度から評価し、修正点をフィードバックします。
この工程を繰り返し、製品の完成度を高めます。
- 見積もり取得・契約締結
最終仕様が固まった段階で、正式な見積もりを取得します。
製品単価、金型などの初期費用、最小発注ロット(MOQ)、納期、支払条件、検品基準などを精査し、双方が合意すれば基本契約を締結します。
契約書の雛形は、日本貿易振興機構(JETRO)の提供するテンプレートなども参考になります。
- 量産立ち上げ・検品
契約に基づき、量産を開始します。
初回の生産時には、仕様通りに製品が作られているかを確認するため「量産立会い検査」を実施することが推奨されます。
生産完了後には、契約で定めた基準に基づき検品が行われます。
- 納品・販売開始・フォローアップ
検品をクリアした製品が指定場所に納品され、いよいよ販売開始です。
量産後も定期的にメーカーと品質に関する情報を共有するなど、良好な関係を維持し、継続的な改善や次の製品開発へとつなげていきます。
OEMの費用構造と価格交渉のポイント
OEMにかかる費用は、主に「初期費用」と「量産費用(製品単価)」に分かれます。
これらの費用構造を理解し、的確な交渉を行うことが、事業の収益性を大きく左右します。
OEMの費用構造
- 初期費用:製品を作るための金型代、木型代、印刷の版代、試作品の開発費用などが含まれます。製品によっては数十万〜数百万円かかることもあります。
- 量産費用(製品単価):製品1個あたりの価格です。これは主に以下の要素で構成されます。
- 材料費:製品に使われる原材料や部品のコスト。市場価格の変動を受けやすいです。
- 加工費・労務費:製品を組み立て・加工するための費用や人件費。工場の稼働率が影響します。
- 管理費・間接費:工場の維持費や管理部門の人件費など。
- 管理マージン:OEMメーカーの利益分。
価格交渉を有利に進めるポイント
単に「安くしてほしい」と伝えるだけでは、交渉はうまくいきません。
相手にとってもメリットのある提案をすることが重要です。
- 発注量のコミットメント:「年間で最低でもこれだけ発注します」と約束することで、メーカーは安定した生産計画を立てられるため、単価を引き下げやすくなります。
- 支払サイトの短縮:支払い条件を「月末締め・翌月末払い」から「当月末払い」にするなど、メーカーのキャッシュフローを改善する提案は喜ばれます。
- 閑散期の活用:メーカーの工場の稼働が落ちる時期(閑散期)に生産を依頼することで、加工費の割引を交渉できる場合があります。
- 仕様の見直し:オーバースペックな部分はないか、より安価な代替材料は使えないかなど、メーカーの専門知識を借りてコストダウンできる仕様を共同で探ります。
価格交渉に関する考え方は、中小企業庁が公開している「価格交渉ハンドブック」なども非常に参考になります。
業界別・OEMの成功事例
OEMがどのように活用され、成功につながっているのか。
具体的な事例を見ていきましょう。
事例1:健康食品メーカーA社(サプリメント開発)
独自成分を配合したサプリメントの製品化を目指したA社についてです。
医薬品レベルの品質管理が求められるため、企画段階からGMP認証を持つ国内の専門工場と提携しました。
メーカーの持つ豊富な処方データとA社の独自アイデアを組み合わせ、短期間で高品質な製品開発に成功しました。
その品質の高さが評価され、全国のドラッグストア約3,200店舗への導入を果たしました。
事例2:家電ベンチャーB社(小型空気清浄機)
設立直後で資金が限られていたB社は、自社での工場建設を断念しました。
代わりに、設計・開発力に定評のあるタイのEMS企業と協業することになりました。
現地の安価な部品を活用しつつ、日本の住環境に合わせたデザインと性能を実現し、企画からわずか8ヶ月で量産にこぎつけました。
B社は製造コストを抑えられた分、マーケティングとブランディングに資源を集中させ、初年度での黒字化を達成しました。
事例3:アパレルブランドC社(国産シャツ)
「メイドインジャパン」にこだわるアパレルブランドC社は、国内の小規模な縫製工場と連携しました。
そして、天然素材100%のオリジナルシャツを展開しました。
この工場は小ロット生産に柔軟に対応できるため、C社は多品種を少量ずつ生産し、顧客の反応を見ながら追加生産する方式を採用しました。
これにより、定番商品の在庫リスクを従来比で50%以上削減することに成功しました。
優良なOEMパートナー選定の6つのポイント
OEMの成否はパートナー選びで9割決まると言っても過言ではありません。
以下の6つの視点から、長期的に協業できる優良なパートナーを総合的に評価しましょう。
- 1. 技術力と実績
自社が作りたい製品カテゴリでの豊富な生産実績があるか。
特許保有数や専門スタッフの資格など、客観的な技術力の高さも確認します。
- 2. 品質管理体制
不良品の発生率や、製品のトレーサビリティ(生産履歴の追跡)体制はどうか。
ISO9001などの第三者認証の取得状況や、工場監査の結果を確認します。
- 3. 財務の健全性
長期的な取引を安心して任せられるか、企業の財務状況(自己資本比率やキャッシュフローなど)を確認することも重要です。
- 4. コミュニケーション能力
問い合わせへのレスポンス速度、言語の壁(海外の場合)、そして何より、こちらの意図を正確に汲み取る必要があります。
課題解決に向けた提案をしてくれる「伴走者」としての姿勢があるかを見極めます。
- 5. 柔軟性と拡張性
小ロット生産への対応、仕様変更の柔軟性、将来的な増産への対応能力など、自社の成長に合わせてくれるパートナーかどうかも大切な視点です。
- 6. 倫理観と環境配慮(CSR)
近年、サプライチェーン全体での人権や環境への配慮が強く求められています。
CSRレポートの開示状況や、サステナブルな素材の採用実績なども、現代における重要な選定基準です。
日本のOEM市場の最新動向と今後の展望
国内のOEM市場は、消費者のニーズの多様化を背景に、新たな局面を迎えています。
経済産業省の工業統計調査や各種民間調査レポートによると、市場規模は拡大を続けており、特に食品と化粧品分野が成長を牽引しています。
近年のトレンドとして、以下の3点が挙げられます。
- パーソナライズ化と少量多品種生産
個人の健康状態や好みに合わせたサプリメントや、多様な肌色に対応するファンデーションなど、パーソナライズ化の需要が急増。
これに応えるため、小ロット・多品種生産を得意とするOEMメーカーの価値が高まっています。
- 環境配慮(サステナビリティ)への対応
リサイクル素材を利用した容器や、環境負荷の少ない製法など、サステナビリティを意識した製品開発が不可欠になっています。
グリーン購入法などに対応した製造ラインを持つことが、メーカーの新たな競争力となっています。
- DX(デジタル技術)の活用
生成AIを活用した需要予測システムを導入し、発注ロットを最適化する動きが始まっています。
これにより、委託者側は廃棄ロスを削減し、受託者側は生産効率を高めるという、双方にとって利益のある関係が構築されつつあります。
業界団体が主催する展示会やセミナーに参加することで、こうした最新動向を肌で感じることができます。
例えば、一般社団法人日本能率協会(JMA)などが主催するイベントは、情報収集の貴重な機会となります。
OEMに関するよくある質問(Q&A)
一般的な目安として、化粧品で300〜1,000個、健康食品で1,000〜3,000個、アパレルで100〜300枚程度からが相場です。
近年は小ロット専門のメーカーも増えており、数十〜100個単位で対応してくれる場合もあります。
一方、輸送に時間がかかる(リードタイム延長)、為替変動リスク、文化や言語の違いによるコミュニケーションの難しさなどがデメリットです。
国内工場は、高品質、小ロット・短納期への柔軟な対応、そして品質トラブル時の迅速な対応がメリットです。
デメリットは、海外に比べてコストが高くなる傾向がある点です。
生産主体はあくまでライセンシーです。
一方、OEMは、生産そのものを外部に委託するモデルであり、製造の主体はOEMメーカー側にあります。
Q. 契約書で特に注意すべき条項は何ですか?
①品質基準と検品方法
②不良品発生時の責任分界点と対応
③知的財産権(開発した製品の権利)の帰属
④秘密保持義務の範囲と期間
⑤契約解除条件と損害賠償
曖昧な表現を避け、具体的な数値を盛り込むなど、弁護士などの専門家にも相談しながら慎重に作成することをお勧めします。
海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!
「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」
そんなお悩み、ありませんか?
越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!
越境EC・海外販路開拓なら世界へボカン!
【OEM関連用語解説】
- プライベートブランド:小売業者や卸売業者が企画し、自社のオリジナルブランドとして販売する商品。PBとも呼ばれる。
- サプライチェーン:製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの一連の流れのこと。
- 国際標準:国際標準化機構(ISO)などが、世界中で同じレベルの品質や安全性を確保するために定める共通の規格。
- ODM:Original Design Manufacturingの略。委託者のブランドで製品を生産する点はOEMと同じだが、製品の設計・開発段階から製造業者が担当する点が異なる。
- 機密保持契約:Non-Disclosure Agreement(NDA)とも呼ばれる。取引を通じて知り得た相手方の営業上・技術上の秘密情報を、第三者に漏洩したり、目的外に使用したりしないことを約束する契約。
- GMP:Good Manufacturing Practiceの略。「適正製造規範」と訳され、医薬品や健康食品、化粧品の製造において、原材料の受け入れから出荷までの全工程で、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準。
- EMS:Electronics Manufacturing Serviceの略。電子機器の受託製造サービスのこと。複数のブランドから電子機器の製造をまとめて請け負う専門企業を指す。
おすすめ記事
アクセスランキング